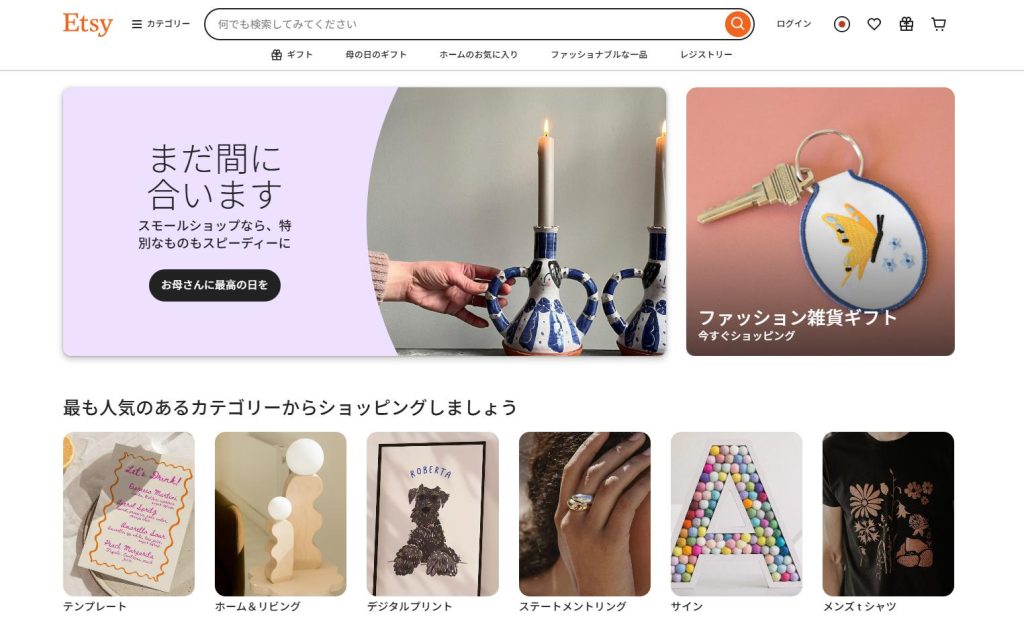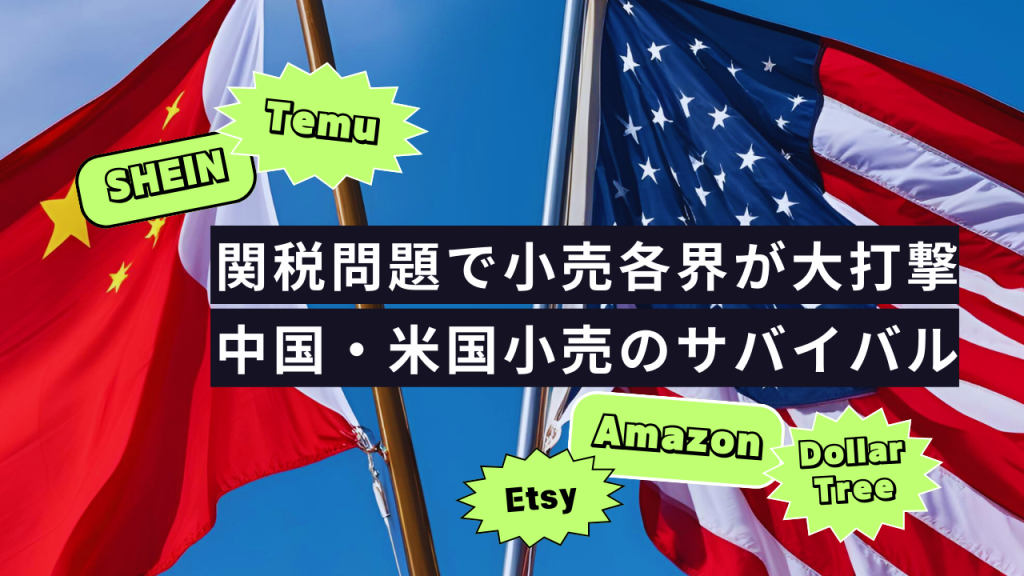
2025年5月2日、トランプ大統領は中国からの輸入品に最大145%の関税を課すと発表し、800ドル(約11万5,000円)以下の海外輸入品にかかる関税や消費税を免除する「de minimis(デ・ミニミス)」制度も廃止しました。この制度は、「SHEIN(シーイン)」や「Temu(テーム―)」といった中国系格安ECの米国市場での急成長を支えましたが、米商務省によると、制度撤廃により、中国からの輸入品には120%の関税、または1パッケージあたり100ドル~200ドル(約15,000円~約29,000円)の手数料が課されることになります(6月から200ドルへ引き上げ予定)。
こうした米中貿易戦争の影響を受け、米国で商品を取り扱う小売企業やプラットフォーム各社は、製造拠点の見直しや価格改定などのビジネスモデル改革を余儀なくされています。
本記事では、動向が特に注目される「SHEIN」「Temu」に加え、ディスカウント小売チェーンの「Dollar Tree(ダラーツリー)」、ハンドメイド作品・資材などを中心に取り扱うオンラインマーケットプレイスの「Etsy(エッツィー)」、「Amazon(アマゾン)」など米国企業各社の対応策をレポートしていきます。
クイックサマリー
SHIEN・Temu|米国で最大377%の値上げ 欧州シフトを加速
4月25日、「SHEIN」「Temu」は米国における大幅な価格改定を発表。両社はこれまで免税制度を活用し、衣類や日用品を低価格で提供してきましたが、一部商品で最大377%の値上げが実施されました。

例えば、厚手のキッチンタオルは1.28ドル➔6.10ドル(約200円➔約950円)に値上げとなり、為替レートにもよりますが、日本円では約4~5倍の価格上昇となっています(2025年5月の為替レート1ドル=約155円目安)。他にも、キッチン用品では61.72ドル➔70.17ドル(約8,900円➔約10,000円)と13.7%上昇、水着セットでは4.39ドル➔8.39ドル(約680円➔約1,300円)と91%上昇。商品によっては価格変動がない場合や、逆に値下がりするケースもありますが、こうした相次ぐ値上げは消費者にとっては大きな負担増となります。
欧州市場へのシフト
米国市場での厳しい状況を受け、両社はヨーロッパ市場への注力を強化しています。2025年4月には、「SHEIN」がフランスで45%、イギリスで100%の広告費増加を行い、「Temu」もフランスで115%、イギリスで20%の広告費増加を実施。また、「Temu」は、米国への直接配送を停止。現地倉庫からの出荷に切り替える「ローカルフルフィルメントモデル」へと移行しました。配送体制の強化により、関税の影響を最小限に抑えることを目指し、物流戦略の見直しを行っています。しかしながら、米国内での新たな倉庫建設などを行う大量生産モデルは環境保護団体からの批判も強まりつつあります。
参照:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-27/shein-hikes-us-prices-as-much-as-377-ahead-of-tariff-increases
https://www.fashiondive.com/news/temu-walks-back-price-increases/747122/
https://www.reuters.com/business/media-telecom/shein-temu-ramp-up-advertising-uk-france-us-tariffs-hit-2025-05-05/
Dollar Tree|もはや100円ショップではない、値上げと商品展開の多様化へ
米国版“100円ショップ”として知られるディスカウント小売チェーンの「Dollar Tree(ダラーツリー)」は、中国・メキシコ・カナダからの輸入にかかる関税強化を受け、一部商品の値上げを検討しています。同社は仕入れ先との価格交渉や製造拠点の見直しなどでコスト増の抑制に努めていますが、関税の影響を完全に吸収するのは難しい状況だといいます。
「Dollar Tree」店舗イメージ(公式オンラインサイトより)
「Dollar Tree」では現在、1.25ドル(約180円)を標準価格として商品展開。従来の低所得層の支持に加え、インフレの長期化により、中・高所得層の利用も増加しています。近年は、約2,900店舗で標準価格(1.25ドル)を超える商品を導入し、一部商品は1.50~7ドル(約215円~約1,000円)で販売されています。競合他社での値上げも相次ぐ状況下にあり、今後は標準価格を1.50ドルや1.75ドル(約215円や約250円)へ値上げしたとしても顧客離れは限定的だと分析されています。
2025年度の売上高は、180億~190億ドル(約2兆5,900億円~約2兆7,300億円)、既存店売上高は3~5%増の見通し。第4四半期の売上高は50億ドル(約7,200億円)で、純利益も増加しました。関税によるコスト増は、月2,000万ドル~最大4,000万ドル(28億8000万円~58億円)の影響が見込まれていますが、現時点でその90%以上を吸収できているとしています。
今後は、仕入れ先の多様化や商品仕様の見直し、非採算商品の削減などを通じて価格競争力の維持を図る方針です。値上げへの警戒感もありますが「お得感重視」の姿勢を貫くことで、幅広い層の支持継続を狙っています。
参照:
https://finance.yahoo.com/news/dollar-tree-gains-citi-upgrade-164704368.html?guccounter=1
Etsy|米国のエンドユーザーに「国内での購入」を呼びかけ 出品者ケアにも注力
米国発オンラインマーケットプレイスの「Etsy(エッツィー)」では、ユーザーと出品者に「国内での購入」を呼びかけています。同社CEOのJosh Silverman(ジョッシュ・シルバーマン)氏は、「関税強化により、サプライチェーンや価格、商品の調達コストに不確実性が広がっている」と発言し、米国内だけでも6,000万点以上の商品が国内発送可能であり、全米各州に数千人の出品者がいることを強調しました。
「Etsy」公式オンラインサイト
「Etsy」では、商品全体の約25%が海外調達ですが、その多くは800ドル(約11万5,000円)以下の「de minimis(デ・ミニミス)」免税枠内に収まっていました。しかし、5月2日以降、中国・香港発の商品すべてに関税が課されたため、今後は価格上昇や配送遅延が懸念されています。UBS証券は「2025年度の『Etsy』全体の流通総額は5.5~11%減少する可能性がある」と予測しています。
そのような状況下で「Etsy」は、出品者支援策として、関税負担や配送遅延による注文キャンセルが発生した場合、出品者の返金責任を免除する制度を導入。また、関税前払い型が可能なDHL(ディー・エイチ・エル)やFedEx(フェデックス)などのクーリエ便の指定を推奨し、追加コストを価格に反映するよう助言しています。
Josh Silverman氏は「今後も規制や関税の動向を注視し、必要な情報を随時提供する」と述べ、国内販売の強化や、価格設定や配送方法に関する中小事業者向けのサポート体制の拡充に努めています。
参照:
https://www.retaildive.com/news/etsy-ceo-josh-silverman-tariffs-buy-domestic/745753/
Amazon|倉庫や物流システムに混乱、中国製商品の発注キャンセルが相次ぐ

米Bloomberg(ブルームバーグ)など米複数メディアの関係者取材によると、4月2日の関税引き上げ発表を受けて、米Amazon(アマゾン)が同日中に中国製製品の一部発注を突如キャンセルしていたことが明らかになりました。キャンセル対象には、ビーチチェア、スクーター、エアコンなど幅広い商品が該当し、ある業者は、すでに生産済の50万ドル(約7,500万円)相当のビーチチェアの注文が「発注ミス」として一方的に取り消されたと証言しています。「Amazon」側はキャンセル理由を明示していませんが、関税回避が主な目的とみられています。
同社は売上の4割を占める、海外メーカー直輸入型の仕入れ=直輸入注文を多用していますが、近年は、直輸入より手数料収入を得られる第三者出品者による販売比率を高める方針を強化。今回の動きもその戦略の一環とする見方があります。
一方で、キャンセルにより生産済みの商品を抱える業者側は、他国市場での販売や他の小売業者との取引を模索せざるを得ない状況です。「Amazon」ではこれまでも、米中貿易摩擦や地政学リスクへの対応を強化しており、今後も経営戦略の一環として柔軟な調達体制の構築を進めていくと見られます。
参照:
https://www.usatoday.com/story/money/2025/04/09/amazon-cancels-china-product-orders/83009150007/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-09/amazon-cancels-some-inventory-orders-from-china-after-tariffs
まとめ
米国による関税引き上げと免税制度の撤廃は、格安ECから大手小売まで幅広い企業に影響を及ぼしています。各社が、他市場への進出、価格の底上げ、国内流通の強化など、関税強化によるコスト吸収と顧客維持のバランスを取りながら、国際情勢に対応した事業運営を模索しているようです。引き続き、世界小売の動向を注視していきます。